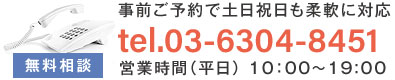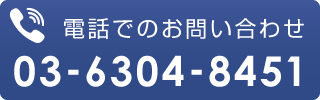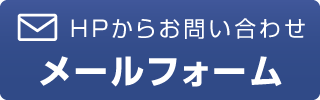Archive for the ‘【遺言相続知識】’ Category
中野区,練馬区,杉並区の相続相談
中野区役所の区民相談では相続相談の割合が非常に多いです。
今回は相続の概要について簡単にまとめていきます。
1,相続はどの専門家に相談するか?
相続といっても,遺産整理,相続放棄,遺言,遺産分割,使途不明金,遺留分侵害額の請求,不動産登記,相続税等と多岐に渡るため,どの専門家に相談したらよいかわかない方が多いと思います。
そこで,まずあらゆる分野に対応できる弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士が相談者の現在の問題になっている事象につき,的確なアドバイスを致します。
特に相続となると,相手方(他の相続人)がいるケースが多いと思います。
そうすると,将来的に交渉や話し合いを行うケースが生じます。その場合には唯一代理人になることができる弁護士にスムーズに依頼することがベストになるからです。
例えば,不動産登記であれば司法書士/相続税の申告であれば税理士ですが,
司法書士や税理士のご紹介なども弁護士を通じで行うことができ,ワンストップサービスを図ることができます。
2,相続問題の視点
相続問題は(1)相続発生前か(2)相続発生後に分類できるかと思います。
順番に説明致します。
(1)相続発生前
相続発生前は,①遺言,②財産管理がよく問題になります。
①遺言
遺言は将来自分が亡くなったときに,自分の財産を誰にどうやって分与するのか自分の意思を予め残しておくことができる文書です。
遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言があります。
遺言を作る際には,相続人の把握,遺産の把握などの前提問題のほか,遺言執行者を誰にするかの問題や遺留分を侵害しない範囲で作成するかなどの法律の知識が必要なところがあります。
そして,せっかく作成したのに無効な遺言では意味ありません。
形式的に不備のない有効な遺言を作成する必要があります。
最近,自筆証書遺言については法務局に遺言を保管できるサービスができました(自筆証書遺言保管制度)。
従来,自筆で作った遺言は死亡後,家庭裁判所で「検認」という手続きを経ないといけませんでした。
しかし,保管制度を利用することで,「検認」の手続きが不要になるメリットがあります。
また,法務局で保管されるので,遺言の紛失のおそれや改ざんのおそれを防止できるメリットがあります。
保管申請手数料は 3,900円とお安いところもメリットです。
どのような種類の遺言を作ればよいのか?
それぞれの相談者の背景事情などをうかがい相談に乗ることが可能ですのでお問い合わせ下さいませ。
②財産管理
将来自分が認知症などになったときに財産の管理をどうしようか?認知症にならなくとも銀行に行くのが大変であるから今のうちから財産の管理をしてもらいたい!また子どもがないから頼む人がいない!
などなど
自分の老後の財産の管理をどのようにすればよいのか?という問題があります。
このときに,任意後見制度,財産管理等委任契約,家族信託などが考えられます。
それぞれの制度にはメリットもデメリットも存在します。
たとえば,任意後見制度は判断能力が低下し,任意後見監督人が選任されたときに契約がスタートするのですが,
財産管理委任契約は,正常な判断能力があるときにも,契約をスタートできるメリットがあります(特に,入院中の支払や外出困難な場合などのお金の出し入れなどは財産管理委任契約に適するかと考えます)。
そして,両者(財産管理委任契約と任意後見契約)を併用することがよく行われます。
つまり,判断能力ありのときの財産管理を財産管理等委任契約として,任意後見監督人が選任されたときに任意後見契約に移行するという方法です。
もっとも,後見契約の場合,家庭裁判所への報告や許可など制約なども生じます。
そこで,家族信託という制度もあります。
これは認知症になっても,資産が凍結されることなく,受託者が信託財産の管理・運用・処分ができるというメリットがあります。
信託契約は公正証書によることが望ましく,委託者(財産を託す人),受託者(財産を管理する人),受益者(財産の利益を受ける人)の3者の契約となり,信託口座を作ることになります。実際には委託者と受益者が同じになることが多いです。
もっとも家族信託は財産の管理や処分を委ねるもので,身上監護の面では不十分であったりします。
したがって,いずれの制度を活用するのがベストなのか各相談者の背景によりますので,個別に相談いただればと思います。
(2)相続発生後
次に,相続発生後の問題について説明致します。
相続発生後は,
速やかに事務手続き(金融機関への連絡,死亡届の提出,年金・保険の死亡届,世帯主変更届)を行う必要があります。
次に法律問題と税金問題などを考えていく必要があります。
税金問題については4か月以内に準確定申告をし,10か月以内に相続税の申告,納付をするなどの税金問題になりますが,本記事では省きます(税理士の紹介は可能です)。
なお,令和6年4月から相続登記などの義務化も始まります(相続から3年以内とされており,司法書士を紹介可能です)。
本記事では法律問題を中心にみていきます。
以下,
①相続人及び相続財産の調査及び確定作業
②遺言書の有無の確認(自筆の場合は検認手続)
③相続放棄
④遺産分割
⑤遺留分侵害額請求
という順番でみていきます。
①相続人及び相続財産の調査及び確定作業
(相続人調査及び確定作業)
まず相続人が誰であるかを確定しなければなりません。
誰が相続人であるかはどうやって確認するのか?
それは戸籍で確認することになります。
よくあるのが聞いていた話と異なり,隠し子がいたり,過去に離婚を数回しており,子供もいたなどです。戸籍を確認してはじめてわかることも多いものです。
そして戸籍を読み解ていく必要があります。
これには相続人の順位と範囲の知識が必要になっていきます。
手順としては以下になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本,改正原戸籍,
・相続人の戸籍謄本
例えば相続人になるべき者がすでに亡くなっているときには代襲相続人が相続人になります。
この場合,代襲相続人の戸籍なども集めるため,戸籍の量が非常に多くなります。
そして,これらの戸籍は銀行や法務局などの手続の際にも必要になります。
戸籍の束を持ち歩くのは大変です。
そこで,現在,法定相続情報証明制度という制度ができました。
これは法務局に戸籍などを提出し,相続情報一覧図を作成すると,
登記官が一覧図に認証文言を付して,この一覧図をもって窓口などで手続きができるようになるものです。
この制度を是非お使いくださいませ。
なお,家庭裁判所の調停などではやはり原則通り戸籍の束が必要なようです(当職の経験)。
(遺産整理~相続財産の調査)
上記相続人の調査と同時に遺産も整理していかなければなりません。
何が遺産かを確定し,はじめて遺産分割協議が可能になります。
遺産はプラスの財産だけはなく,マイナスの財産も遺産です。
そこで,すべての遺産を洗い出し,それに関連する書類をすべて集める必要があります。
そして,正確な額を記入した遺産目録を作成していく必要があります。
現在,遺産整理という業務も流行りとなっております。
関係書類の取得その他をすべて専門家に任せることができます。
ただ相続人の一人が勝手にやると後で他の相続人からクレームが入ることなどもあります。
なので,弊所は遺産整理は他の相続人に異議がないことを確認した上でのみ依頼可能となります。
②遺言書の有無の確認
遺言は,生前の被相続人の意思が反映されたものです。
遺言がある場合,記載された内容どおりに分割を行います。
もっとも,遺言の種類によっては手続きもことなります。
たとえば自筆証書遺言で自筆証書遺言保管制度を利用していない場合は裁判所で「検認」の手続が必要になります。
この場合,封を空けてはいけません。
また,遺言執行者が誰であるかも問題なります。
遺言については下記の記事でも書いておりますので,参照くださいませ。
また,
複数の遺言が見つかった場合はどうなるか?,
相続人全員の合意で遺言に従わないこともできるか?
などの論点も存在します。
そして,付随する問題としては,遺言無効確認訴訟や遺留分侵害額請求などがあります。
そもそも遺言作成時に認知症だったということで争いなることもよくあるものです。
そうならないための対策などもご相談にのることが可能です。
③相続放棄
今まで相続前提に書いてきましたが,もちろん相続をせずに,相続放棄をすることも可能です。
相続放棄をすると,法律上はじめから相続人でなかったことになります。
したがって,プラスの遺産もマイナスの遺産も引き継がないことが可能になります。
もっとも相続放棄は期限に注意してください(3か月以内にしなければなりません)。
※ 熟慮期間(3か月)の延長の手続もあります。
この点,
相続放棄をすべきなのか?
取得分なしとする遺産分割協議をするのか?
どちらでも変わらないのではないないか、という問題があります。
しかし,当職の見解では借金は遺産分割協議では免れることができませんので,借金に焦点をあてると,取得分なしの遺産分割協議ではなく,相続放棄をするほかないと考えます。
相続放棄については下記の記事を参照ください。
④遺産分割
ようやく遺産分割となっても,遺産分割は相続人全員が参加し,全員が合意する必要があります。
そのため,1人でも反対する者がいたり,連絡がつかない者がいたりすれば,遺産分割は争いになってしまいます。
そこで,弁護士に相談,依頼し,交渉・審判・調停などでまとめていく必要があります(140万以上の案件で代理人になることができる専門家は弁護士のみです)。
遺産分割協議,調停については下記記事を参考にしてみてください。
そして,この遺産分割のなかでは,生前や死後の使途不明金などが争いになっている事案も多いです。
使途不明金があるから,遺産分割ができない事案は山ほどあります。
使途不明金について詳細に記載したので下記記事を参照にしてみてください。
⑤遺留分侵害額請求
相続人の1人に全部あげるという遺言があったします。
すると,他の相続人は何ももらえないのでしょうか?
答えはもらえます。
なぜでしょう?
それは法律上,遺留分という最低保証の権利があるからです。
遺留分侵害額請求権というもので,これは侵害された遺留分を相手に対して金銭で支払いを求めることができる権利になります。
また,遺留分の計算対象は遺言だけなのかといえば,そうではありません。
よく問題なるのが生前贈与になります。
・相続開始前「1年以内」の相続人以外への生前贈与
→ 1年以内の贈与の判断は契約時が基準になります。
・相続開始前「10年以内」の相続人への特別受益にあたる生前贈与
→ よくある事例は不動産を買い与えた,住宅資金を出した,借金を肩代わりして支払った,
婚姻のため若しくは生計の資本として贈与したなどの事案があげれられます。
・遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与
→ 贈与当時に損害を加える認識で十分で加害の意思までは必要ではないとされています。
は遺留分の計算対象になります。
遺留分侵害額請求については下記の記事を参照にしてみてください。
______________________________
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟
親の囲い込み問題(介護と相続)
1,高齢化社会で生じる兄弟間の紛争
高齢化社会では今まで以上に「親の囲い込み」と「親の財産の使い込み」事案が増加すると考えます。
「親の囲い込み」と「親の財産の使い込み」は兄弟間の紛争に位置づけです。
※「親の財産の使い込み」について,別の記事で書いておりますので,こちらを参照ください→「親の財産の使い込み」
この記事では「親の囲い込み」について考えていきます。
2,親の囲い込みとは?
「親の囲い込み」とは,兄弟の一方が介護などを理由に親を連れ去って,匿ってしまうことです。
どのような問題が生じるのでしょうか?
・真意ではない遺言が作られるおそれがある
・親の財産の使い込みのおそれがある
問題が生じなくても,そもそも親と面会・連絡することができないのはおかしいと考えるのが普通です。
一方的に面会・連絡を遮断されてしまった側は,親と面会・連絡する権利の妨害に対してはどのように争っていくべきなのでしょうか?
3,横浜地方裁判所平成30年07月20日決定
面会・連絡する権利の妨害に対しては,面会妨害禁止の仮処分の申し立ての方法があります。
参考になる裁判例としては,横浜地方裁判所平成30年07月20日決定があります。
兄弟の一方が認知症の両親を施設に入所させて,一方に会わせないようにした事案です。
同決定では,
「子が両親の状況を確認し、必要な扶養をするために、面会交流を希望することは当然であって、それが両親の意思に明確に反し両親の平穏な生活を侵害するなど、両親の権利を不当に侵害するものでない限り、債権者は両親に面会をする権利を有するものといえる。」
として,面会妨害禁止の仮処分を認めました。
ここで重要なのは「それが両親の意思に明確に反し両親の平穏な生活を侵害するなど、両親の権利を不当に侵害するものでない限り」という条件が記載されていることです。
つまり,認知症ではない事案の場合,両親の意思なども重視される可能性があるという点です。
また,同決定を分析していくと,面会妨害禁止の仮処分の手段以外にも多くの手段があり,それを実施していかないと面会妨害禁止の仮処分が認められない可能性もあると読み込めました。
以下,「親の囲い込み」事案について通常考えられる手段を記載していきます。
4,面会妨害禁止の仮処分以外の手段
(1)交渉
兄弟で対立している場合,当事者で話し合いができない可能性があります。この場合は,第三者にまずは相談してみましょう。
弁護士などに依頼をし,住所の調査をはじめ,面会を求めていく交渉をしていくことが考えられます。
(2)虐待事案の場合
また,虐待事案の場合には高齢者虐待防止法に基づき,行政に動いてもらう必要もあります。
虐待とは同法律から抜粋すると以下のような定義になってます。
◆「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
◆「養介護施設従事者等による高齢者虐待」
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
(3)親族間の紛争調整の調停申立て
交渉が困難であった場合に次に考えられるのが親族間の紛争調整の調停申立てです。
裁判所から抜粋します。
「親族間において,感情的対立や親などの財産の管理に関する紛争等が原因となるなどして親族関係が円満でなくなった場合には,円満な親族関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,親族関係が円満にいかない原因などについて,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をします。」
もっとも,あくまで調停は交渉の延長でもあります。話し合いなので相手が欠席したり,拒否すると不成立になってしまいます。
(4)親の後見開始の申立て
親が認知症である場合は,後見開始の申し立てをすることが考えられます。しかし,親が認知症であることの診断書が必要であるところ,診断書は連絡すらとれない状況では入手できないこともあります。
となると,そもそも申立てすら難しいことになります。
申立てができたあと,鑑定医の鑑定を本人が受けるかという次の問題も生じます。
事案に寄りますが,少なくとも上記(1)~(4)の実施は面会妨害禁止の仮処分を求めていくには必要だと考えました。
(5)その他(慰謝料請求)
債権者は両親に面会をする権利を有する場合(それが両親の意思に明確に反し両親の平穏な生活を侵害するなど、両親の権利を不当に侵害するものでない限り)には,その権利侵害として不法行為に基づき損害賠償請求を求めていくことが考えられます。
__________________________
お気軽にお問合せくださいませ。※現在案件が多く取り扱っていません。
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟
遺産分割と使途不明金(遺産の使い込み問題)
(事案)
亡くなった母の通帳から多額の出金履歴が判明。母と同居していた兄が引き出したに違いない。
遠方に住んでいた弟が,兄からお金を返してもらいたいと事務所に相談に来ました。
(問題)
使途不明金や(贈与があったものとして)特別受益性が問題になります。
どのように解決していくかは,事案によって異なりますが,下記にまとめておりますので参照ください。
↓
遺留分減殺請求
①遺留分減殺請求をしたい方
②遺留分減殺請求をされた方
からのご相談を受け付けております。
遺留分とは何か,誰が請求できるものなのか,具体的な割合等について説明したうえで,
弁護士に依頼すると何をしてくれるものなのかを簡潔に書いてきたいと思います。
遺留分・遺留分減殺請求とは何か?
遺留分とは,相続人なら必ず貰える財産の割合ことをいいます。
遺留分減殺請求とは,遺留分(相続人なら必ず貰える財産の割合)を取り戻す請求のことをいいます。
たとえば,長女と次女の2名が相続人であるときに,「全ての遺産を次女に相続させる」という父の遺言があったとしましょう。
長女は相続できないのでしょうか?
民法は,長女が最低限相続できる財産を「遺留分」として保証しています。
この場合,長女は次女に対して,遺留分減殺請求をすることができるのです。
他にも,「愛人等の第三者に贈与」,「後妻に贈与」などの事案でよく問題になります。また,「親と暮らしていた兄弟と離れていた兄弟間」などでも,親から贈与を受けていた(特別受益)ということで争いになることもあります。
遺留分減殺請求権者は誰ですか?
兄弟姉妹以外の相続人とその承継人です。
兄弟姉妹は遺留分減殺請求ができないのです。
請求が必要で,時効もあるので注意ください。
遺留分減殺請求をするには,遺留分が侵害されているといえなければなりません。また,遺留分が侵害されていたとしても、請求をしなければ,そのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されてしまうことになりますので注意が必要です。
請求をしなければ,と記載したとおり,遺留分減殺請求には,時効があります。時効は,「①相続の開始及び②減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」から1年です。②の調査の多少時間がかかっても,発見したら迅速に動くことが必要になります。
遺留分の割合はどうなっていますか?
それぞれの遺留分として認められている割合は,財産全体の遺留分の割合に各自の法定相続分をかけたものになります。
例として1200万円の遺産があったとします。
以下の場合は全体としての遺留分は遺産の1/2,金額は600万円です。
配偶者のみ ― 600万円(1/2)
配偶者と子 ― 配偶者300万円(1/4),子300万円(1/4)
配偶者と子二人 ― 配偶者300万円(1/4),子150万円(1/8)ずつ
配偶者と親 ― 配偶者400万円(1/3),親200万円(1/6)
子のみ ― 600万円(1/2)
これらの場合は全体としての遺留分が1/2です。
相続人が親のみの場合,全体の遺留分は1/3となるため,金額は400万円です。兄弟姉妹のみが相続人になる場合,遺留分は認められていませんので,遺留分はゼロです。
このような遺留分を侵害する相続がなされた時,侵害された遺留分を確保するために,財産を相続した人に対して,遺留分減殺請求をする必要があります。
弁護士に相談・依頼するメリット
相談時には,相続人や遺産の範囲を確認できる資料や遺留分侵害を確認できる資料をご用意いただきたいです。
↓
①侵害行為の特定
②相続人や遺産の範囲の確認
③遺留分率の確定
④相手方の特定
⑤時効などの確認
⑥侵害額の概算
いったところを調査・分析していきます。
↓
また,遺留分減殺請求をする前に,遺言書がある場合には遺言無効の主張ができないかどうかというところを分析していきます。遺言無効が可能な場合には,主位的に遺言無効確認,予備的に遺留分減殺請求といったかたちをとることが多いです。
↓
多くの事案は,交渉(内容証明郵便等),協議などをしていきます。
弁護士が代理人になるので,すべてお任せいただけます。
遺言無効確認訴訟のポイント
遺言書がある場合,遺留分減殺請求の前に,遺言が無効にならないか検討します。
遺言が無効であれば,原則として法定相続分どおりになるので,遺留分減殺請求をするよりも大きなメリットがあるからです。
遺言の無効事由は,形式要件(①方式違反,②共同遺言,③証人立会人の欠格事由)と実質要件(①遺言能力の欠缺,②公序良俗違反,③錯誤無効,詐欺取消し等)に分類されており,いずれかを欠けば無効の主張が成り立ちえます。また,遺言者の死亡前に,受遺者が死亡していれば,遺言は効力が生じません(民法994条)。
最も問題になるのは,実質要件の遺言能力の欠缺です。
相続放棄
相続放棄の相談を受け付けております。
✔「相続放棄という制度は知っているけど,やり方がわからない。」
✔「相続放棄すべきか,相続すべきか判断に迷っている。」
✔「3か月過ぎてしまった。相続放棄はできないのではないか。」
✔「相続放棄の申述期間の延長ができないか。」
このようなお悩みがある方は,気軽にお問い合わせください ⇒ クリック
1, 相続放棄とは?
お亡くなりになられたご両親の負債(借金)が資産より多いとき,相続放棄をすれば,負債(借金)も資産も受け継がれないということになります。
被相続人の負債(借金)が多いとき,相続人側にとって「相続放棄」という制度は,大変助かる制度になっています。
相続放棄後は,次順位の相続人に負債や資産が受け継がれることになります。
もっとも,次順位の相続人も相続放棄をすることができます。
したがいまして,相続放棄をする場合は,次順位の相続人との関係なども重要になります(事前に通知しておくのか,一緒に相談にくるのか)。
2,相続放棄の手続きの概要と弁護士に依頼するメリット
相続放棄とは,その名のとおり,遺産相続を放棄する手続きです。
1,家庭裁判所に申述という法律行為を行わなければならないこと
「何の書類を集めたらよいかわからない」
「何度も区役所や市役所に行くのが大変だ」
「申述書を弁護士の名前で書いてほしい」
「何度も訂正するのが大変なので不備なくやってほしい」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
2,プラス財産(不動産・過払い金)のほうが多く相続放棄をする必要がない場合の判断
「相続放棄したほうがいいのか,資産も負債もあるので受け継いだほうがいいのかわからない。もしかしたら負債のほうで流行りの過払い金が発生しているかもしれない。」
「土地建物(不動産)を持っており,売却すれば借金を返済できるかもしれない。借金を返済してもプラスの財産が残るかもしれない。」
他にも,「土地建物(不動産)を失いたくないので,借金を相続して,自分が任意整理して(利息カットでの分割払い)返していきたい。」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
3,相続放棄は,一定の行為をすると,できなくなってしまうこと
「相続放棄の前にどういう行為をしたら,相続放棄ができなくなるかわからない。
お父さんの車は乗ってていいの?遺品の整理はしていいの?スーツやネクタイはもらっていいの?生命保険金はもらっていいの?」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
※処分に該当する行為をすると相続放棄はできなくなる
民法921条1号は処分に該当する行為をすると,相続放棄ができなくなると規定しております(単純承認)。
よく相談が多いのは,葬儀の執行や保険金の請求や形見分けなどです。
葬儀費用は,相当の費用であれば,セーフです。
保険金の請求も受取人に指定されてるものであればセーフです。
もちろん例外もありますので,慎重に判断しなければなりません。
形見分けも原則OKですが,例外もありますので,慎重に判断する必要があります。
4,相続放棄は,3カ月という期限があること
「負債の調査に時間がかかるから,延長はできないの?」
という場合には,弁護士に相談することが重要かと思います。
3,借金の調査はどのように行うべきか
借金の調査は,届いた請求書や督促状や,亡くなった方のカード関係から把握することができます。
より正確に把握するためには,信用情報機関(CICやJICC)に問い合わせをして,信用情報を取得する必要があります。
相続人であることを証明するための戸籍関係や定額小為替や申込書などを作成すれば,郵送等で取得手続きをとることができます。
4,会社の代表者だった場合
よくある相談が,亡くなった方が会社の代表者で,借金をたくさん抱えていた場合です。
会社の借金は個人の借金とは別なので,全く無関係かと思われますが,会社の債務は個人のほうで連帯保証人になっている可能性が高いです。また,取引先から代表者に対する損害賠償請求権が成り立つ場合もあったりします。
この場合,連帯保証債務や損害賠償債務等も相続されることになるため,債務の加えて考えていく必要があります。
会社の税理士等と相談して債務を把握していかなければなりません。
5,相続放棄の費用等
相続放棄の弁護士費用は1人あたり10万円(税別)+実費(戸籍などの取得費用や郵送費や印紙代)で承っております。
複数人依頼の場合の値引きもございます。
相続相談
相続相談といっても,遺産分割,相続放棄,遺留分,使途不明金,遺言・・・と多岐に渡ります。
弊所は相続法改正を踏まえて,あらゆる相続問題を扱っています。
簡潔に初回相続相談の概要を説明致します。
1,初回相談で持参いただきたい資料
(1)相続関係説明図
相談の段階がいつの時点かによりますが,全分野に共通する事項として,相続関係説明図を持参いただきたいと思います。
弊所でも用意はしておりますが,相続の相談の際には,まずは相続人等の確定が必要になります。
法務局HPから抜粋致します。下記にて相続関係図をダウンロードできます。
相続人が誰だかわからないという事案も多々あります。この場合はわかる範囲で結構です。
依頼前提である場合は,戸籍関係も持参いただくとスムーズです。
(2)遺産(資産,負債)一覧メモ(及び裏付け資料)
相談の段階がいつの時点かによりますが,全分野に共通する事項として,遺産一覧メモ(及び裏付け資料)を持参いただきたいと思います。
メモは手書きで大丈夫です。
遺産は,主に,
資産,①預貯金(銀行,支店名,口座番号),②株式(証券会社名,銘柄),③その他金融商品,④不動産(全部事項証明書,固定資産評価証明書,査定書),⑤生命保険(生命保険の種別,受取人名),⑥高価な動産(写真,査定,取引価格),⑦債権(取引先,個人,借用書その他の書類),等です。
負債,⑧借金(債権者名,債務額,契約書)などです。
また,①~⑧を裏付ける証拠ものちのち依頼後には必要になりますので,取得できる範囲で集めていただけるとスムーズです。
もちろん,遺産として何があるかわからない段階の相談も多々あります。この場合はわかる範囲で結構です。
(3)その他
関係しそうな資料一切です。
遺産分割や遺留分の相談は,「遺言書」がある事案は,必ず遺言書を持参ください。
2,依頼後の流れ
(1)遺産分割の事案
事案によって異なりますが,相手に受任通知を送り,協議から始めます。
相手に弁護士がついた場合は,弁護士同士で協議を行っていきます。
もちろん中には調停からという事案もあります。
協議が決裂するようであれば,調停前置主義が採用されているため,遺産分割調停を申し立てることになります。
なお,相続法が改正されているため,配偶者居住権等を踏まえて考えていく必要もあります。
(2)遺留分
遺留分は,相続法が改正され,遺留分減殺請求権が金銭債権となり,その名が遺留分侵害額請求権となりました。
今までは遺留分を請求すると,共有となり,共有関係の解消という別問題が生じていたところ,お金だけで解決するという改正がされたのです。
遺留分についても,遺産分割と似ており,まずは額を確定するために内容証明郵便で通知することからはじまります。
そのあと,協議→調停と進みます。
遺産分割協議・調停
遺産分割協議・調停は弁護士に気軽にご相談ください。
遺産分割協議・調停の一般的な流れと当事務所の特徴等をご説明致します。
遺産分割の目的
・遺産分割協議
被相続人の遺産は,亡くなると同時に,相続人全員の共有となります(遺言がある場合を除く)。
相続人全員の共有の遺産を各相続人に具体的に配分する話し合いが必要となります。その話し合いが「遺産分割協議」です。
「遺産分割協議」を行って,遺産分割協議書を作らなければなりません。
遺産分割協議書がないと,銀行,法務局,証券会社等での手続きや税金の確定等ができなくなってしまします(預金等は凍結状態のままとなってしまいます)。
また,遺産分割協議書がないまま,遺産を分けない状態で月日が流れれば,更なる相続人間の間でもめ事などが発生してしまいます。
・遺産分割調停
遺産分割協議が揉める場合は,家庭裁判所に「遺産分割調停」を提起しなければなりません(調停前置主義)。
「遺産分割調停」で話し合いがまとまれば調停調書ができあがりますので,それが協議書と同じ役割を果たします(調停調書は執行力も付与されます)。
・調停に変わる審判
調停がわずかな相違で合意に至らないとき等には家庭裁判所が調停に代わる審判をする制度もありますが,2週間以内に異議を出せることもできます。
異議があったときは,調停不成立の場合と同様に,次の遺産分割審判に移行することになります。
・遺産分割審判
家庭裁判所が,陳述の聴取や審問を経て,審理を終結させ,審判をします。
もっとも,審判に対しては,即時抗告ができます。
最終的に高等裁判所によって決定を出してもらうことになります。
・地方裁判所での民事訴訟での解決
遺産の範囲で争いが生じている事案については,民事訴訟で遺産確認の訴えを提起する必要があります。
当事務所の強み
・税理士などと連携しワンストップサービスを実現します
・フットワークが軽いので代理人として交渉・立ち会いを積極的に行います(弁護士以外に依頼すると法律上交渉はできないので注意して下さい)
・相続登記も司法書士をつけずに可能です
遺産分割協議の流れ
1,相続人調査
戸籍謄本等で確認致します。
なお,相続人の範囲に異議がある場合や相続人が行方不明の場合は,法的に解決する必要があります。
2,遺言書の有無の確認
(1)遺言書あり
遺言書に相続先が全て決まっていれば,遺言書どおりに遺産を分割します。
※ 自筆証書遺言 → 開封NG → 家裁で検認の手続きが必要になります。
遺言の形式や内容や有効性等に争いがあれば,民事訴訟で解決していくことになります。
(2)遺言書なし
遺産分割協議を行います。相続人全員の参加と合意が必要です(遺産分割協議書の作成)。次の3以降を参照。
3,遺産分割協議
(1)相続分の確定
法定相続分に基づき相続分を確定します。もっとも,相続人全員の意思で,法定相続分と異なる合意をした場合,自由に相続分を決めることができます。
(2)遺産の範囲の確定
プラスの財産も,マイナスの財産も遺産です。法律や判例で遺産になるものとならないものなど正しい知識が必要になります(生命保険金?香典?葬儀費用?)。
遺産の範囲が確定できなければ,民事訴訟で法的に解決していくことになります。
(3)遺産の評価
遺産となるプラスの財産とマイナスの財産を評価します。不動産や株式は個別に評価をします。
不動産や株式の評価は,業者等に査定してもらうことになるとともに,税金の問題もあるため,税理士等との連携も必要になります。
(4)特別受益や寄与分の決定
特別受益: 一部の相続人に遺贈や生前贈与があると,他の相続人に比べて多くを相続していることになります。そのため,遺産分割の際には,特別受益の持戻しをして手続きをします。
寄与分: 被相続人に対して特別な貢献(例えば事業従事,看護など)があると,寄与度として確定し,法定相続分に上乗せして,遺産を取得することができます。
(5)遺産分割方法の決定
(1)~(4)で取得分額を決め,取得分額に従って,遺産の分割をしていきます。分割方法は,次の4種類あります。
・現物分割
不動産屋等の財産をその現物のまま各相続人に分割する方法です。
・換価分割
遺産を売却して,お金にして分けやすくして,相続分の金額を各相続人に分割する方法です。
・代償分割
特定の相続人が,相続財産をそのまま現物で取得し,その人が他の相続人に相続分の金額を支払う方法です。
・共有分割
相続人で,遺産を共有する分割の方法です。
(6)遺産分割協議書の作成
話し合った内容を,正式な条項にて協議書というかたちでまとめていかなかればなりません。
【遺言問題】公正証書遺言のススメ
● 普通方式による遺言の種類
①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言の3種類があります。
● 自筆証書遺言とは
①「自筆証書遺言」は,遺言者が手書きで作ることができるので,費用も時間もかからないものです。
もっとも,デメリットとしては,
・法律上の要件を備えていないものであれば無効になる
・毀棄・隠匿・偽造の危険がある
・相続開始後に家庭裁判所に「検認」の手続きをとらなければならない
といったことがあります。
法律上有効な遺言書を確実に作成したい方,遺言書を確実に保管しておきたい方にはあまりおすすめできるものではありません。
● 秘密証書遺言
③「秘密証書遺言」は,公証人役場で保管するもので,誰にも内容を知られないものです。遺言書を確実に保管できるところは,①よりもよいです。
もっとも,デメリットとして,
・公証人がその内容を確認するわけではないので,形式に不備があったりする場合は無効になる危険がある
・相続開始後に家庭裁判所による「検認」の手続をとらなければならない
といったことがあります。
● 公正証書遺言のススメ
そこで,②「公正証書遺言」というものがあります。
公的な証書であるというだけなく,公証人が事実関係等を録取の上,法律の規定に則った手続を履践して作成することから,法律上の要件を欠くことなく,有効な遺言書を確実に作成できます(①や③のデメリットを回避)。また,原本は公証役場に保管されますので,遺言書の紛失,破棄,隠匿の危険がありません(①のデメリットを回避)。家庭裁判所の「検認」の手続きも必要ありません(①や③のデメリットを回避)。
ということで,確実性を重視するならば「公正証書遺言」がおすすめといえます。
ただし,公証人役場に行く必要があることや証人を2人みつけなければならないことや手数料がかかります。
公正証書遺言は,弁護士に委任することで依頼者様の負担はある程度軽減され,手続はより確実なものとなります。相続人の範囲を確定し,相続財産を調査し,事情や希望をお伺いして,遺言案を作成するので,内容的に漏れのない確実なものを反映させることができます。それをベースにしたものが公正証書遺言になっていきます。
そして,公証役場に書類を提出する際に公証役場に行って公正証書遺言を作成してもらう日を決めることになります。公正証書遺言を作成してもらう日には,依頼者様も一緒に同行することになります。
● 公正証書遺言+αが必要な時代
さて,遺言について説明してきましたが,本当に遺言だけで対策は十分なのでしょうか?!
遺言書は,主に遺産の分け方を定めるもので,死亡時に効力が生じるものです。
そこで,
①死亡前に「寝たきり・要介護状態」や「認知症」になったとき等の財産の管理等には別途契約書を作っておく必要があります。
②死亡後の事務処理についても別途契約書を作っておく必要があります。
契約書の名称は「財産管理等委任契約書」「任意後見契約書」「死後事務委任契約書」等というものです。
これらの契約書も公正証書化をしましょう。任意後見契約は法律では公正証書化しなければ,効力が生じないものとされています。
したがいまして,当事務所では公正証書遺言の作成の依頼の際には,その他の契約書の作成に意向等もお伺いしながら,お客様にあった最適なサービスを提供するように心がけております。
相続とお金の使い込みの争い~使途不明金問題
1,使途不明金とは何か
亡くなった方(「被相続人」といいます)の預金通帳や取引履歴をみると,
死亡前または死亡後に複数回にわたり,多額の預金の引出行為がなされていることがあります。
※ よくある事案
たとえば,被相続人(母)には子が3人(A,B,C)いるとしましょう。
Aは母と同居して母の介護をしていた。B,Cは遠方に住んでおり同居していません。
B,Cが,母の預金から多額の預金が引き出されていることを知って,「全部Aがやったんだ。返せ。」と言う事案です。
既に亡くなっているので,亡くなった本人に自分で引き出したのか・お金はどこにあるのかといった事情を聞くことができません。
事情を知っている相続人がきちんと説明し,その説明が合理的で,他の相続人が納得をすれば争いにはならないかもしれません。
しかし,説明があやふやで領収書などの証拠なども保管していないと,争いになってしまうことが多いです。
このような使途不明金の問題については実務ではどのようになっているのでしょうか。
どのように解決していくのでしょうか?
2,使途不明金は実務ではどのように扱うか
(1) ①死亡前の使途不明金と②死亡後の使途不明金
①死亡前の使途不明金は,返還を求める側から贈与の主張がでる場合,遺産分割における特別受益の問題になります。
他方で,贈与の枠組みで解決しない場合,一般的な使途不明金の問題になり,返還を求める側は不当利得であることの立証責任を負います。
②死亡後の使途不明金は,遺産分割前の相続預金の払戻制度で払い戻しを受けた場合,遺産の一部分割があったものとみなされます。
他方で,同制度を利用していない場合,一般的な使途不明金の問題になり,返還を求める側は不当利得であることの立証責任を負います。
※ 遺産分割前の相続預金の払戻制度被相続人の預貯金額×1/3×払い戻しを希望する相続人の法定相続分。但し、同一銀行から払戻しを受けられる金額は相続人各150万円が上限になります。
(2) ①死亡前の使途不明金の立証責任
返還を求める側は不当利得であることの立証責任を負います。
まず問題になるのが引出行為者です。
ア、被相続人が引き出していたのか,
イ、相続人の1人が引き出していたのか,
が問題になります。
アの場合,不当利得とはいえなくなります(もっとも被相続人が引き出した金員が相続人に渡っているところが証明できれば贈与といえる可能性があり特別受益の問題とします)。
イの場合は,被相続人が同意していたのかが問題になります。
同意していない場合は,意思に基づかないものとして,他の相続人が,勝手に引き出した相続人に返還請求を求めていくことになります。
同意していた場合は,金員の行方によっては不当利得または贈与と扱っていくことになります。
たとえば,被相続人が寝たきりの場合などは同意はないといえるでしょう。
次に問題になるのは金員の行方です。
相続人の1人が自分の為に使った,自分の口座に入れたなどの事実を証明できるのであれば,返還請求権の証明は十分でしょう。
他方で,金員がどこにいったかわかないという事案は多いです。この場合,「被相続人の必要経費だった」という反論がよくあります。
この場合,返還を求められている相続人が必要経費を裏付ける領収書などで,合理的な説明をしていくことがメインとなってきます。
(3)②死亡後の使途不明金の立証責任
上記同様,返還を求める側は不当利得であることの立証責任を負います。
もっとも,死亡前と異なり,死後なので,被相続人の同意はないことが明白です。
したがって,金員の行方だけがメインの争点となります。
前述したとおり,「被相続人の必要経費だった」という反論,
つまり,返還を求められている相続人が必要経費を裏付ける領収書などで,合理的な説明をしていくことがメインとなってきます。
たとえば,入院費用,携帯代,電気代,交通費などは必要経費にあたる場合が多いです。
3,弁護士に依頼をした場合,使途不明金はどうやって解決していくか
(1)請求する側と請求されている側(交渉レベル)
弁護士は請求側も被請求側も相談に乗ります。
まずは証拠分析と立証計画を立てます。
したがって,通帳履歴,取引履歴のほか,たとえば領収書,家計簿,診断書,払い戻し用紙,カルテなど関係しそうな資料をすべて持参してもらうことになります。
そのあと,遺産分割協議中なのかそうなのか等を含め,手続き関係を決めていきます。通常は交渉解決ができないかを考えます。そのほうが迅速で費用面でもお得なためです。
もっとも,交渉が難しい場合,裁判所の手続きにしたがって解決していきます。
(2)調停での解決
もっとも,払い戻しをした当の本人が同意をしない場合が多いため,民事訴訟で遺産の範囲の確認の訴えや不当利得返還訴訟をしなければならず,非常に遠回りで時間がかかるものでした。
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)という条文が設けられました。
- 第906条の2
- 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
- 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
この規定により,実際の払い戻しをした相続人の同意はなくても,他の相続人の全員の同意があるときは,遺産分割の対象として存在するものとみなすことができるようになりました。
なので,調停で遺産分割調停のなかで話し合いをすることが容易になりました。
もっとも,同条文は注意が必要で,引出行為者に争いがない場合を前提にしていると解釈できますし,引出行為者や金員の行方などで,争いがある場合は結局話し合いは決裂となり,
(3)訴訟での法律構成