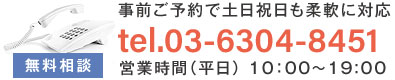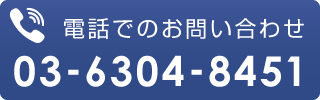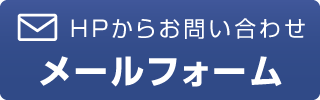Archive for the ‘【債権回収知識】’ Category
マッチングアプリでの金銭トラブル
マッチングアプリ等で知り合った男女間の金銭トラブルが増加しております。
マッチングアプリ,出会い系などの他,XなどをはじめとするSNSで知り合った金銭トラブルも多いです。
どのような金銭トラブルが多いのでしょうか?当職の体感で第1位から第5位までを簡単に書いていきます。
第1位 お金の貸し借り
お金に困っている女性と女性を助けたい男性の間でのお金の貸し借りでの金銭トラブルです。
弁護士の視点で分析すると,
借用書の有無,それがなくてもLINE上などでの「貸す」「返す」等の返還の合意などが立証できるか問題になります。
また,手渡しなのか,振り込みなのかが問題になります。
そのうえで,いつまでに返すのかという弁済期の定めの有無が問題になります。
そして,これらの分析の前に相手の素性,住所などを把握しておく必要があります。
次には不法原因給付ではないかも問題になります。
これらについては,詳しくは下記の2つの記事をお読みいただければ理解できます。
①愛人関係の記事
②愛人関係でも返金できる可能性の記事
第2位 投資による預託金
この手口は様々ありますが,一般的にはお金を増やすから出資してほしい,預けてほしいという
ことで最初の数回は返金などがあるが,以後音信不通になるという事案です。
しかも注意が必要なのが最初の数回の返金のあとに,追加出資などを頼んでくるのです。
いわゆる投資詐欺のような金銭トラブルになります。
このような金銭のトラブルは男女でのみならず,同性同士でも非常に多いです。
詳しくは下記の副業詐欺や投資詐欺の記事をお読みくださいませ。
第3位 貞操権侵害
男性が既婚者であるのもかかわらず,独身であることを装って女性と肉体関係を持ち,
後日何らかの理由で既婚者であることがバレルと言う事案です。
このような場合,女性は貞操権侵害を理由に男性に慰謝料請求をすることができることがあります。
この金額や事実関係などを巡る金銭トラブルが多いです。
第4位 結婚詐欺
事案により様々ですが,結婚すると偽って交際を開始し,多くのお金を騙し取るいわゆる結婚詐欺
での金銭トラブルがあります。
第5位 妊娠詐欺
また,妊娠していないにもかかわらず,妊娠したと偽って,お金を騙し取る金銭トラブルがあります。
いずれも事実関係や金額を巡り争いが生じます。
お問い合わせ
男女間の金銭トラブルは無料相談になります。
いずれも早期相談が解決につながります。
弁護士にお気軽にお問い合わせくださいませ。
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟
投資詐欺や副業詐欺等でお困りの方
近年,インターネットを通じて,様々な投資に関する詐欺が横行しております。
どのよつか投資詐欺が多いのか?仮に詐欺に至らなくても不法行為といえる場合もあります。
そもそも,このような問題を弁護士に依頼したところで返金の可能性がどの程度あるのかについて説明致します。
投資詐欺
金融庁の登録を受けている金融商品取引業などを行う者か否かをまず確認する必要があります。
登録を受けている業者は金融庁のホームページで確認できます。
インターネット上の投資関連のページ内にある広告をクリックすると無登録の業者に繋がるようになり、無登録の業者は「これから急騰する銘柄を教えます」「FXで1000倍」などと謳い、高額な費用を振り込ませる、ということがよくあります。
投資関連のページと記載しましたが、
例えば、金融庁から登録を受けてる業者を比較するサイトや、銘柄を紹介するような普通のサイトにも、詐欺の広告が潜んでいます。
そのような詐欺の広告をクリックしてしまい、無登録の業者に関わってしまい、お金を振り込んだ場合、返金は非常に困難です。
業者の住所と会社名で登記簿を取り寄せても存在してない、つまり架空の業者の可能性があります。
また、LINEなどの連絡手段だけで契約書などもなく、いずれそのLINEアカウントも消えてしまいます。
振り込め詐欺救済法に基づき、振り込んだ先の口座凍結をすることで、返金される可能性はありますが、時は既に遅しです。
無登録業者も巧妙であり、足取りがつかない違法に入手した口座を利用しており、当然、振込後にすぐに出金されております。
振り込め詐欺と似た構造があります。
※なお、口座を売るバイトをして、その後の事情を知らないだけでも、口座を売った方も詐欺や犯罪収益移転防止法違反などの罪に問われます。
適合性の原則や説明義務
上記は振り込め詐欺と同様の事案でそれ自体犯罪になりうるものですが、
犯罪にはならないレベルで巧妙な手口も多く存在します。
そして,グレーゾーンだと警察も民事不介入として動かない。
業者の登記簿自体は存在しており、契約書などごある場合でも、
当該投資勧誘、助言が不法行為の要件を満たす場合にも返金の可能性はあります。
判例上、適合性原則違反や説明義務違反に対しては、不法行為上の違法と判断されているので、そのような要件を満たすかなどを慎重に検討していきます。
近年では様々な手口も
SNSやマッチングアプリやLINEで知り合った方から資金を運用する・FXの運用・海外FX口座開設するなどという誘いをうけて、大金を預けたものの、返ってこなかったなどの事案も多くあります。
最初は分配金などを支払うことはあっても、最初だけで、そのあとは音信不通になっていくパターンです。
最初にいくらか分配金を支払うのは信頼を得てお金を積ませるためです。
基本的に、他人から勧誘される投資話はすべて詐欺(若しくは詐欺要素があるもの)だと考えても良いと思います。
特に、契約書もなく、ラインや電話のみという場合は注意してください。
弁護士に依頼すると?
投資詐欺は返金の可能性が著しく低いのが特徴であり、返金は確実だと謳い、高額な着手金をとる弁護士もいるようです。
そのようなことで二次被害を受ける可能性もあります。
もっとも、やはり相手が判明しており、住所などもわかってる場合、弁護士をいれることで回収確率はぐんと高まるのも事実です。
当職は、弁護士名で通知を送り、お金を実際に回収したこともあります。
問題は相手が判明や所在が不明な場合なのです。
なので実際に弁護士から言われた着手金などの金額がものすごい高い場合、複数の弁護士に「この金額で弁護士に依頼するのが本当に良い事案なのか?」ということを相談した方がよいです。
気軽にお問い合わせを
気軽に関までお問い合わせください。
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟
パパ活と貸金と不法原因給付の考察
パパ活という言葉流行り,世の中にはパパ活にまつわる様々な法律問題が生じています。
今回はパパ活における法律問題のうち,金銭問題に絞って解説をします。
パパ活関係の法律相談
パパ活関係ではストーカーや詐欺など色々と法律問題がありますが,
もっとも多い分野は,男性が女性に貸したお金の返還を求める事案です。
男性は女性との関係を維持するために,お金に困っていると言う女性にお金を貸します。
最初のうちは男性は女性と週1回程度会って,連絡もとれていたのですが,次第に女性と連絡がとれなくなっていきます。しまいには音信不通にまでなってしまった・・・?
男性はハッと目が覚めたかのように女性に貸したお金を返してもらいたいと強く思うようになり,弁護士に相談します。
双方の主張・反論
男性側の弁護士は①金銭の授受,②返還の合意などを立証し,貸金返還請求をしますが,
女性側の弁護士はもっぱら肉体関係を目的とした契約は公序良俗に反し無効であり,貸付金は不法原因給付に該当するため、返還を請求できない。
と反論します。
民法708条は不法の原因に基づいて給付した者からの返還請求を否定する条文です。
法律用語で不法原因給付といいます。
その趣旨はどのようなものなのか?
社会的に非難されるべき行為をした者が自分の損失を取り戻そうとしても法は救済しませんよ(クリーンハンズの原則)という趣旨です。
となると,男性は貸したお金を取り返せないの?????
条文を形式的に適用すると取り返せないように読めますが,裁判例を考察していくと一概にはそういえません。
不法原因給付に関する裁判例の考察
以下,簡単に裁判例を考察していきます。
東京地判平成27年2月18日判決
1,女性の積極的働きかけを契機として貸付けに至ったものであると推認されること(貸し付けの経緯)
2,男性の貸付けの目的が、女性との肉体関係を継続させることのみにあったとまでは認め難いこと(貸し付けの主要な目的)
3,本件貸付けの使途
4,本件貸付後の状況
といった1~4の諸事情を考慮し,本件貸付けが公序良俗に反し、同貸付けに係る金員交付が不法原因給付に当たるということまではできない。
と判断して,男性側が勝ちました。貸したお金を返してもらえる判決になったのです。
もちろん実際の裁判例では事実関係が詳細に記載されております(今回は省略しております)。
実際は当該事案の事実関係こそが重要になりますが,
大きな視点として1~4などの諸事情を考慮し,裁判所は不法原因給付かを形式的ではなく,実質的に判断するものだということがわかります。
東京地判平成30年3月6日判決
こちらは理由を抜粋します(D1 LAW引用)。原告と被告をわかりやすく男性と女性に変えました。
「女性側は、男女の関係を持つことの対価として男性側が女性側に金銭を交付する旨の合意に基づいて男性側が女性側に金銭を交付してきたものであるとして、本件契約の成立を否認する。
男性と女性が知り合った経緯に照らすと、男性が女性に対して金銭を交付した背景に両者間の男女関係があった可能性は否定できない。
しかしながら、同関係の形成や維持の対価として金銭を交付する旨の合意の成立を認めるに足りる証拠はないから、女性側の前記主張は認められない。」
として,女性側の証拠不十分として、男性側が勝ちました。お金を返してもらえるという判決になったのです。
こちらの裁判例は最初に紹介した裁判例と異なり,裁判所は実質的に不法原因給付にあたるかどうかという判断はしてません。
逆に金銭を交付した背景に原告被告間の男女関係があった可能性は否定できないとしてる点も注目です。
そして,女性側が主張している肉体関係の形成の維持や対価としての金銭を交付する合意がないとしています。
話を進めると、この裁判例は女性が勝つには「肉体関係の形成の維持や対価としての金銭を交付する合意」が必要とまで言ってることを読み込むことができます。
そうなると,女性が不法原因給付で貸金の返還を免れるには例えば肉体関係一回につき◯万円を借りるなどの金銭消費貸借契約書などを作っておかなければならなかったといえます。
もっとも事実関係を分析していくと,本裁判例は男性と女性で通常の準消費貸借契約の契約書が作成されている事案であり,
女性もサインをしている以上、その契約書が重視されているのかもしれません。
まとめ
以上,パパ活にまつわる不法原因給付の話でしたが,
民法708条は形式的に適用されるというわけではなく,
事実関係による,
男性側も勝てる可能性があるということを伝えたく,
本記事を書きました。
お気軽にご相談ください
気軽に関までお問い合わせください。
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟
予防のための債権回収(信用調査や担保権の設定)
債権回収は,支払停止時(いわば緊急時)のものですが,
予防のための債権回収は,取引前・取引時に行うものでもあります。
予防のための債権回収として,相手の調査やどのような契約書を交わすかが重要になってきます。
取引相手の信用調査
取引を行う相手方の会社に信用があるかは大切なポイントです。
多額の借財がある(多数の債権者がいる)会社と取引したら,不良債権になってしまうのは目に見えております。
弊所では,取引先の会社の不動産登記簿謄本と会社履歴事項全部証明書を持ってきていただき,相談にのることが可能です。
可能であれば,決算書も持ってきてください。
EDINETや会社四季報の未上場版でみることができなければ,すでに債権者である場合,会社法442条3項を使って開示請求をして取り寄せます。
なお,大きな取引の場合は,調査会社を使うことも多いです。
基本契約書や個別契約書の作成
継続的取引全体に適用される基本契約書を作成すると,その後の取引はスムーズにいきます。
基本契約書を作成しておけば,個別契約の契約書は事細かなものではなくても済みます。
合意事項を明確にするには,基本契約書と個別契約書をわけて作成していくことをおすすめします。
担保権の設定
万が一のことを考慮し,担保権の設定をしておくことが,債権回収の最大の予防策となります。
実際には,業界の取引通念上,見積書や注文書だけである場合も多く,結果として「契約書もない・担保権も設定しておらず」,いざ債権回収のために動いても,回収不能(不良債権)の事案は後を絶ちません。
担保権の設定にあたり,担保権はどのようなものがあるか以下説明していきます。
担保権には,物的担保と非典型担保と人的担保があります。
物的担保
法定担保物権(留置権や先取特権)は法律上生じるものですので,特に設定は不要です。
約定担保物権の典型例は,抵当権です。
抵当権は設定が複雑で,抵当権の実行も裁判所を利用しなければならず,煩雑です(競売手続)。
抵当権は「不動産」に設定するものですが,実際は既に多額の融資を受けている会社等には金融機関の抵当権がついてしまっている場合があります。
相手の社長の個人宅にもついている場合があります。
非典型担保
非典型担保は民法上の上記物的担保以外のもので,実務上・裁判上認められているものです。
①動産譲渡担保
たとえば,債権を担保するために,重機の所有権を債権者(譲渡担保権者)に形式上は譲渡しており,債務者(設定者)は重機を利用します。債務者(設定者)が遅滞をしたら、債権者(譲渡担保権者)は,重機を処分する権限を取得します。
譲渡担保は,裁判所を利用せず,私的実行が可能なところに特徴があります。
第三者との関係では,動産譲渡登記ファイルで対抗要件を具備することが可能(法人の動産)。
※集合物譲渡担保
たとえば,債務者が大きな倉庫を所有していて,そこで日々商品が出入りしている場合に,商品をきちんと特定していれば,集合物として担保の設定が可能なのです。
判例では,種類,場所,量的範囲を指定し,目的物の範囲の特定は必要となっておりますので,要件を満たすきちんとした契約書を作成する必要があります。
②債権譲渡担保
債権を担保するために,債務者(設定者)が第三者に有する債権(売掛金等)を譲渡するかたちで担保を設定するものです。
形式的には債権譲渡の方法で行われるため,第三者対抗要件や債務者対抗要件を具備する必要があります。法人が債権を譲渡した場合,譲渡登記によって第三者対抗要件を具備できます。
※集合債権譲渡担保
動産が集合物として担保権を設定できたのと同様,現在および将来の債権を包括的に譲渡担保の目的にすることも可能です。
③所有権留保
例えば,高額な楽器を分割で買った場合,代金が完済されるまで楽器の所有権は楽器屋さんにあって,代金完済時に買主に楽器の所有権が移転するものです。買主は使用収益できますが,支払いを怠った場合は楽器を引き上げられてしまいます。
人的担保
保証や連帯保証があります。
一般的には取引先の会社の代表者に連帯保証人になってもらうことが多いと思いますが,資力・信用がきちんとあるかが大切です。誰に連帯保証人になってもらうかは非常に大切です。会社が倒産するときは,社長も個人破産をすることが多いからです。
保証と連帯保証の違いについて述べます。
大きな違いは,①催告の抗弁と検索の抗弁が保証にはあるが,連帯保証にはない(補充性の有無),②付従性の有無,③分別の利益の有無です。
①のみ簡単に書きます。
催告の抗弁
保証人の場合,債権者からの請求があっても,まずは主債務者に催告を求めるようにいうことが可能です。
他方,連帯保証人には上記のようなことはいえません。
検索の抗弁
保証人の場合,債権者が主債務者に催告した後でも,主債務者に弁済資力があり,かつ,執行が容易であることを証明すれば,債権者は主債務者の財産の執行をしないといけない。
他方,連帯保証人には上記のようなことはいえません。
連帯保証というのは実質主債務者と同様の責任を負うため,非常に強力な担保です。
最後に
債権回収のお悩みは,気軽に弊所に相談ください。
貸したお金
貸したお金を返してほしい。
弁護士が頻繁に扱っている相談です。
貸したお金を返してほしいが,
✔「相手の住所がわからない」
✔「借用書がない」
✔「どうやって返してもらえるかわからない(債権回収)」
いろいろな相談があります。
元交際相手(男女)や友人,さらに親族間など相談は多岐にわたります。
事業主間もあります。
今回は,経験談も交えて,貸したお金を返してもらう方法を簡潔に書いていきます。
貸したお金を返してほしい
貸したお金を「返して」※1というには,まずは貸し借りの契約を主張しなければなりません。契約は,「①当事者の合意(返還の合意)」のみならず,「②貸主から借主に対し金銭等が実際に交付(金銭の授受)」により成立します。つまり,お金を交付していることが契約の成立要件です※2。なお「①当事者の合意(返還の合意)」に書面であることは要求されていないので,口頭でも可能です。
まとめると,
①当事者の合意(返還の合意)
②貸主から借主に対し金銭等が実際に交付(金銭の授受)
という2つの要件があってはじめて,契約は成立するのです。
次に,契約の成立の主張を前提に,「返して」という権利を発生させるには,
返還時期の合意がある場合は,返還時期の合意と返還時期の到来を主張する必要があります。
返還時期の合意がない場合は,返還催告と催告後の相当期間の経過を主張する必要があります。
※1 貸したお金を返してもらう請求
貸したお金を返してもらう請求をすることを,貸金返還請求といいます。
より正確には,金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権です。
なお,過去に貸したお金やお金以外の物を給付する義務を負っている場合,まとめて,お金を貸す契約にすることもできます(これを「準消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」といいます)。
※2 改正民法587条の2
書面でする消費貸借等でお金の交付を要件としない規定が新設されました(諾成的消費貸借契約)。
これは,現代社会において家を購入する際には銀行などとローンを組むのが一般的であり,消費貸借がお金の交付を要件とすると,銀行から確実に融資を受けられる保証がないことが踏まえられています。他方書面という要件を課して,口頭での軽率な合意を防止しました。
貸したお金を返してもらう権利と事実の証明(立証)
上記のとおり,
①当事者の合意(返還の合意)
②貸主から借主に対し金銭等が実際に交付(金銭の授受)
③(返還時期の合意がある場合)→返還時期の合意+返還時期の到来
(返還時期の合意がない場合)→返還催告と催告後の相当期間の経過
を主張して,貸したお金を「返して」もらう権利が生まれるのです。
次に,立証しなければなりません。
立証とは,証拠をあげて要件に該当する事実(①~③)を証明することをいいます。
ここで,皆さんのご存知のとおり証拠が必要になってくるのです。
返還の合意(①)の証拠として,皆さん御存知の借用書があります。
借用書は無敵とも思われますが,作成の経緯や記載内容で,無敵とはならないこともあります。
他方,「借用書がないとだめなのか?」という相談もありますが,なくても大丈夫な場合があります。
前述のとおり,書面であることは要求されておらず,口頭でも返還の合意が可能です。
メールや録音やその他の書類(覚書やメモなど)や当事者の関係性などもみていき,証明できる可能性は十分あります(実際弁護士に相談される事案は借用書よりもこちらのほうが多いと思います)。
現在,コミュニケーションのツールとしてはメールよりもLINEでやりとりすることが多いため,最近の訴訟でもLINEが証拠として提出されることが非常に多いです。LINEで返還の合意を立証できた事案も多々あります。
立証できるのかは,各証拠を弁護士にみせて分析してもらう必要があるかと思います(弁護士に相談するメリットがあります)。
金銭の授受(②)の証拠として,上記①の証拠のほかに,金銭の動きの証拠が大事になっていきます。原資はどこにあったのか,相手は金銭をなぜ必要としていたのか,相手はその金銭を何に使用したのかをはじめ,いわゆる「金銭の流れ」を1つずつ追っていく必要があります。
よく使う証拠としては,通帳の振込履歴などです。
貸したお金を返してもらいたいが相手の住所がわからない
「相手の住所がわからない」というのもよくある相談です。
事案によりますが,私の経験からすると,相手の過去の住所,実家の住所,携帯電話の番号(解約済みでもOK),勤務先などがわかっていればそこから弁護士会照会や職務上請求により,相手方の現住所まで辿れることがあります。
ここで,1つだけ注意点があります。
「住所だけ調べてくれないか」という相談者がいますが,弁護士のルール上,住所調査だけの依頼を受けることができません。
弁護士はあくまで,交渉や訴訟等を前提とした相手方の調査しかできません。
弁護士に住所を調べてほしいという希望の方は,事件として全体を依頼しなければなりません。また弁護士は開示した住民票などを依頼者に交付することもできません。
ご了承ください。
貸したお金を返してもらう方法について
貸したお金を貸してもらう方法の話に移ります。
手段は債権回収の方法と同じです。
債権回収の方法は弊所のページをみてください。
弁護士はまず相手に資力があるか,資産としてどのようなものがあって,何を把握しているのかを聞きます。事案によりますが,交渉に入る前に(内容証明郵便送付前に),仮差押えという手段をとることが最適な場合があるからです。
民事執行法の改正により回収が容易になる可能性(財産開示手続利用)
訴訟のなかで和解をする(和解調書)
訴訟で判決をとる(判決書)
公正証書をつくる(強制執行受諾文言付公正証書)
等,債務名義を獲得すると,確定証明をとり,相手の資産に差し押さえをする権利が発生します(給料,不動産,預金,車など)。
もっとも,相手の資産を把握していないと,差し押さえは困難になります。
となると,債務名義をとっても,意味のない(回収できない)事態が生じてしまいます。
従来から財産開示手続という強制執行の手段がありました。
財産開示手続は,強制執行をしても完全な債権の回収ができなかった場合等に,裁判所が債務者を呼び出して,非公開の期日において,債務者に自己の財産について陳述させる手続です。しかし,裁判所から呼び出しがあるにもかかわらず,債務者は無視をしたりするため,ほとんど利用されてはいませんでした。
今回の改正では,無視した場合には,刑事罰(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることとなり,罰則が強化されることになりました(改正法213条1項6号)。
また,債務名義の種類にかかわらず,財産開示手続の申立をすることが可能とされていました(改正法197条1項柱書)。
さらに,情報開示の対象となる財産は,不動産,給与債権,預貯金・株式等で,裁判所が情報を各機関から取り寄せて開示してくれるようです。
不動産に関する情報取得手続については登記所から,給与債権については市町村や日本年金機構等から,郵貯金や株式等は銀行や証券会社から,開示を受けることができます。
ただし,給与債権は,養育費や生命・身体等の損害賠償請求権に債権が限定されています。
弁護士への相談は早いほうがいい
男女間であれば「別れてから」,友人間では「音信不通になってから」,相談されるかたが多いです。
ただ,手遅れであり,証拠が残っていないことも多いです。
弁護士への相談は早いほうがよいと考えます。
なお,弊所はお金を貸す側,借りる側問わず,完璧な契約書を作成するサービスも行っております。
ネットに出回っている契約書関係は穴だらけです。
契約書作成の単発の相談も受け付けております。
貸金返還請求の弁護士費用
請求額によりますが,着手金交渉5万5000円~承っております。
事案によりますので気軽にお問い合わせください。
文責:弁護士 関 真悟
クーリングオフ
クーリングオフ
クーリングオフをご存知でしょうか?
クーリングオフは,
①特定商取引法のクーリングオフ対象取引であること,
②クーリングオフの意思表示を発信したこと
等を主張立証することで,無条件で契約の申込みの撤回又は契約の解除ができるものです。
「契約をしてしまったが,契約を白紙にしたい」「契約をしてお金を払ってしまったが,契約を白紙にしてお金を取り戻したい」という場合にはクーリングオフができないか?
をまず検討することになります。
クーリングオフ対象取引かどうかの判断が必要
クーリングオフ対象の取引を把握
クーリングオフの対象取引は,決まっています。
訪問販売,電話勧誘販売,連鎖販売取引(マルチ商法など),特定継続的役務契約(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス),業務提携誘引販売取引(内職商法,モニター商法等)です。
通信販売(ネット通販など)は?
通信販売はクーリングオフの対象ではありませんでしたが,近時通信販売の広告で返品特約に関する記載を表示しなければならないという改正がされました。
広告に返品特約に関する記載をルール通りに表示していた場合は,その限りではありませんが,広告に返品特約に関する記載がなければ,8日以内に返品は可能です(ただし送料は購入者側負担)。
どの企業も「返品についての独自のルールなど」を設けているのが通常なので,購入前には返品・返金等のルールを必ず読むべきです。
店舗に出向いての契約は?
店舗に出向いて契約する場合はクーリングオフの対象にはなりません。
もっとも,探偵との契約の場合,カラオケやホテルのロビーや喫茶店等で契約をすることが多いです。このような場合は探偵との契約は,訪問販売としてクーリングオフの対象になります。
クーリングオフには期限があるので注意する
クーリング・オフは申込書面または契約書面のいずれか早いほうの「受領日」から8日以内(初日算入※なお一定の取引は20日以内)に,クーリングオフの意思表示を事業者に発信しなければなりません。
もっとも,
・ 書面を受領したとしても,その書面が「法定書面」といえなければ,8日間の起算はされず,いつでもクーリングオフできることになります。
・ クーリングオフは発信主義をとっていますので,事業者にクーリングオフの意思表示は到達したのが8日以上経っていても,送った日付が8日以内であれば(その証拠は必要),クーリングオフは法律上有効です。
法律上有効な書面を作る
クーリングオフは法律上証拠が残るかたちで行なう必要があります。
FAX,電子メールなどでも,証拠上明確なときは有効と認められる余地がありますが,のちのち争いにならないためにも配達証明付内容証明郵便により,解除の意思表示を行うことが必要です。
クーリングオフが認められない場合
クーリングオフが認められない場合でも,特定商取引法の不実告知等の取り消しという法律手段があったり,消費者保護法や民法の規定で救済できる場合もあります。
弁護士費用
クーリングオフは,交渉段階では完全成功報酬制で依頼が可能です。
詳しい費用はお問い合わせください。
未払医療費の回収
未払医療費回収サービス
当事務所では未払医療費回収サービスを行っております。
未払医療費等でお悩みの病院,クリニック,動物病院,歯科医院等は気軽にお問い合わせください。
弁護士に回収業務を委任・委託するという選択肢
病院やクリニックを経営しており,
未回収金(未払医療費・入院費・手術費)がある場合,
「低額でもよいから早期に債権を買い取ってもらいたい」
「手数料を支払ってもよいからすぐに現金化したい」
と考えるかもしれません。
サービサーへの委託やファクタリング業者との契約等,病院・クリニックの資金繰りの対策は,色々考えられるかもしれませんが,本当にそれでよいのでしょうか?
「弁護士に回収を委任する」ことも一つの選択肢になります。
弁護士に回収業務を委任・委託するメリット
弁護士に回収業務を委任・委託することでどのようなメリットがあるのでしょうか?
業務に集中することができること
回収できるかわからないものにエネルギーを投資することは経営を逼迫させます。
回収業務を弁護士に投げてしまうことで,経営者・従業員は本業に集中することができます。
住居不明者の転居先が特定できる可能性があること
電話に出ないどころか,「宛てどころ尋ねあたらず」で請求書が戻ってきていますことがあります。
弁護士であれば職務上請求をかけることで,住民票を取得することができます。
費用対効果の問題になりますが,23条照会で各携帯会社に所有者を確認できる可能性もあります。
代理人として相手方と法的な交渉ができること
未払の理由が病院側に落ち度がある等の理由であることもあります。
ただのクレームなのか・過失が認められる事実関係があるのか調査をしたうえで,法的な交渉をしていく必要があります。
あらゆる手続きを制限額なしに代理人としてできること
弁護士は交渉代理業務と裁判代理業務を主軸とした資格です。
いずれも制限額なしに行うことのできる唯一の資格なのです。
また,どの手続きをとるかは,事案によりますのでその判断も重要です。
相手方の財産を把握しており,訴訟中に処分される恐れがある場合には仮差押えを行うことも考えていきます。
対応可能な病院・クリニック
①歯科医院
②動物病院
③美容整形外科
④大学病院
⑤総合病院
⑥個人開業医・クリニック
対応地域は特に限定はしておりません。
たとえば東京都外からのお問い合わせもありますので,都外の方も気軽にお問い合わせください。
すべてに共通するのは支払わない理由の特定とそれに基づく方針の決定と解決です。
更には,事例を活かしてトラブルの未然防止策とリスクマネジメントが必要になります。
弁護士費用
当事務所は法律顧問契約により,
着手金0円,報酬金20%+実費により医療機関等の医療費等の回収の依頼を受け付けておりますので,気軽にお問い合わせください。
なお,当事務所は債権回収以外にも上記の顧問契約により,労務関係の相談(採用・退職・損害賠償・給料)や事業承継,経営者の離婚関係の相談や遺産相続の相談も受け付けております。
ゴルフ会員権預託金返還
ゴルフ会員権預託金返還の弁護士無料相談
ゴルフ会員権預託金返還の弁護士無料相談を承っております。
当事務所の預託金返還交渉の弁護士費用
①相談料0円,
②実費込の手数料1万5000円~3万0000円(税別),
③報酬金を回収額の20~25%,
いわゆる完全成功報酬制に近いかたちにしております。
ゴルフ会員権の問題は,債権回収というより消費者被害の分野かもしれません。
以下,簡潔に説明していきます。
預託金の返還について以下のお悩みありませんか??
・150~500万円もの預託金を支払って会員になったが,高齢でゴルフには行かなくなった・コースにも愛着がなくなった。
・父のゴルフ会員権を相続したが,自分はゴルフはしないので預託金の返還を考えている。
・父が亡くなるまえに,ゴルフ会員権を処分して現金にしておきたい。
・預託金返還の抽選に申し込んで数年が経ったが,1度も当選したことがない。
このような方々がいるかもしれません。
いざ返還を求めると,
ゴルフ場やその経営をしている親会社は「据置期間の延長の決議があったのでまだ返すことはできません」「事情が変更したので返すことができません」「経営が厳しいので,誰にも返してません」「抽選式で返還をしていますので当選した場合のみ返還します」等いろいろな事情を理由に返還に応じてくれません。
預託金返還請求権の法的性質と争点
では預託金の法的性質はどうなっているのでしょうか?
裁判をしたら負けてしまうのでしょうか?
以下説明していきます。
預託金返還請求権の性質と発生原因についての説明
預託金の法的性質は消費寄託と言われております。
寄託という名のとおり,ゴルフ場に預けているお金であって,据置期間(5~10年が多い)が経過すれば,全額が退会時に返還されるものです。
法律の要件として,何を証明すれば,返還請求権として構成することができるのでしょうか?
それは以下の4つになります。
①会員契約の成立
②会員契約に基づき金員を預けたこと
③据置期間の満了
④退会の申出
ゴルフ場側からの反論は様々~メインは据置期間の延長?
返還を求めたい側は,上述した①~④の要件を主張立証すれば,返還請求権は発生することになるのですが,ゴルフ場側も様々な反論をしてきます。
ゴルフ場側がしてくる反論は,据置期間の延長という反論が多いです。
※ これは上述した③の要件である据置期間の満了の事実と両立し,その要件を覆すものになります。
具体的には,「総会決議で据置期間を延長したので,据置期間は満了しておりません。」という反論をしてくることが多いのです。
では,このような反論は通用するのでしょうか?
ア)東京地裁平成28年5月25日判決抜粋
据置期間の延長の決議について次のように判示しています。
「据置期間経過後に退会の上預託金の返還を請求し得る権利は、会員の契約上の基本的権利というべきものであって、被告の一方的判断によって安易にその権利を制限すべきでないから,本件延長決議に原告が拘束されると解するのは相当でない。」
イ)最高裁昭和61年9月11日判決抜粋
「・・・本件ゴルフクラブは、いわゆる預託金会員の組織であつて、上告会社の意向にそつて運営され、ゴルフ場を経営する上告会社と独立して権利義務の主体となるべき社団としての実体を有しないことが明らかであるから、本件ゴルフクラブの会則は、これを承認して入会した会員と上告会社との間の契約上の権利義務の内容を構成するものということができ、会員は、右の会則に従つてゴルフ場を優先的に利用しうる権利及び年会費納入等の義務を有し、入会の際に預託した預託金を会則に定める据置期間の経過後に退会のうえ返還請求することができるものというべきであり、右会則に定める据置期間を延長することは、会員の契約上の権利を変更することにほかならないから、会員の個別的な承諾を得ることが必要であり、個別的な承諾を得ていない会員に対しては据置期間の延長の効力を主張することはできないものと解すべきである。もつとも、本件ゴルフクラブの会則七条には、「天災、地変、その他不可抗力の事態が発生した場合は、理事会の決議により据置期間を延長することができる。」との但書があるが、「天災、地変、その他不可抗力の事態」に該当すべき事実については、原審のなんら認定しないところであり、また、会則三〇条には、理事会の決議によつて会則の改正ができる旨が定められているが、本件ゴルフクラブの組織としての前示の性格、会則を改正する機関及びその手続、会則七条但書の据置期間延長について定める厳格な要件などに照らして考えると、預託金の据置期間を延長するような会員の契約上の基本的な権利に対する重大な変更を伴う会則の改正は、既に入会した会員に対する関係においては、会則三〇条の予定するところではないものと解すべきである。」
ウ)まとめ
預託金返還請求権は会員の契約上の権利なので,延長決議には拘束されないのです。
したがって,ゴルフ場の反論はとおらず,会員側が勝つのが原則であると考えられます。
なお,最高裁の判旨の冒頭をよく読むと,ゴルフクラブが法人でない社団にあたる場合は,延長決議も可能のように読めますが,実際に法人でない社団と認定される可能性は極めて低いのはなでかいと考えます。会員とゴルフ場経営会社の2者間の契約と認定されることが多く,それゆえ,延長したとしても,会員の個別的承諾が必要になるのです。
ゴルフ場が経営難であることは事実であること
といっても,ゴルフ場も経営難なのは事実であることが多いです。
もともとは,ゴルフ会員権を市場で売却することが想定されていたようですが,バブル崩壊により売却ができなくなり,いざ返還を求められたゴルフ場の会社には資力がないとうのです。
会員側としてはゴルフ場が経営難で最終的に破産されてしまってはどうしようもありません。
そこで,妥当なところで和解をするのです。
このあたりにの見極めは弁護士にお任せください。
弁護士に依頼するメリット
ゴルフ会員権の預託金返還請求を弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
1,弁護士名義の内容証明郵便による回収率が高まる(法律の要件を漏れなく列挙します)。
2,弁護士が交渉することで,返還に応じることがある(満額は困難:当事務所の回収経験3%~50%)。
3,訴訟提起,訴訟追行が可能(場合によっては事前に仮差押えをする)※訴訟上の和解においても満額は困難で,更に分割払いになることが多い。
4,強制執行が可能。
といったところです。
お問い合わせ先
ゴルフ会員権の預託金返金弁護士無料相談実施中
お気軽にお問い合わせくださいませ。
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟