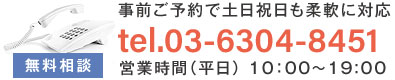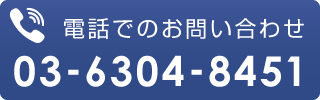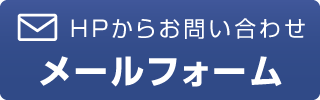音信不通の相手とどうやって離婚をするのか?
過去に多くの音信不通の相手との離婚の依頼を受けてきましたので,当職の経験談を踏まえ,以下説明していきます。順番にやるべきことを記載しています。
目次
1,現住所の調査
ア 職務上請求により相手の引っ越し先の住所を把握していきます
職務上請求という弁護士が弁護士会の指定用紙を使い,定額小為替などを購入すれば,相手の住民票,住民票の除票,戸籍の附票といった現住所把握に必要な書類を獲得することが可能です。ただし,この職務上請求だけを依頼することは不可能となっています。職務上請求をするにはそのあとの交渉や調停がセットになっています。つまり,交渉や調停び依頼が住所調査の必要不可欠な要件となっています。
イ 弁護士会照会により携帯電話の登録先(請求先)住所を把握していきます(単体の依頼が不可能なことは上記のとおり)。
弁護士会照会は弁護士会から携帯キャリア会社に電話番号の登録住所を開示してもらう手続きになります。これには所定の手数料がかかります。携帯のキャリアをある程度把握しておかないと,その分手数料がかかってしまいます。もっとの引っ越しをしても個人情報の変更をしていない方も多いので,その場合はこの方法では住所を把握することができません。
ウ 若しくは実家にいる可能性なども調査していきます。
2,現住所の把握と協議離婚の可能性
現住所の把握ができれば,交渉は可能となります(協議離婚の可能性)。
若しくは,現住所の把握ができなくても,SNSや携帯電話番号がわかれば交渉が可能な場合もあります。
もっとも,相手と何らかの方法で接触ができたとしても,相手が対応しない・無視することもあります。
その場合は次の3へ移行します。
3,離婚調停
相手が応じないならすぐに裁判して離婚をしたいと思われる方も多いですが,離婚の場合は調停前置主義(家事事件手続法257条1項)が採用されており,まずは必ず調停を申し立てなければならないこととなっています。
調停は,相手の現住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
たとえば,相手が三鷹市に居住していれば東京家庭裁判所立川支部に,相手が中野区に居住していれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)に申し立てます。
相手が調停に出席することで,調停での離婚の話し合いが行われていきますが,音信不通の相手方は調停にも来ない可能性が高いです。
相手が調停に来なくても,1回目で調停が不成立になることはないです。
裁判所としても相手を呼び出して,相手の意向を確認してから不成立にしたいという意向があるようです。
過去の当職の経験では,相手方が調停に来ないため,調停委員会の判断により,出頭勧告(家庭裁判所調査官が期日への出席を働きかける手続)がなされたことがあります。
そして出頭勧告をしても,相手方が調停に来ない場合,2回目若しくは3回目の期日で調停不成立となります。
そして,不成立の調書を取得すれば,はじめて下記4の訴訟手続きに移ることが可能になります。
4,離婚裁判(離婚訴訟)
調停が不成立になったら,はやめに離婚訴訟を提起することがおすすめとなります。
調停不成立等の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起した場合には,調停申立ての際に収めた手数料に相当する額を控除できるからです。
離婚訴訟も通常の民事訴訟と同様,相手が欠席なければ,【すぐに勝訴判決を得られる!離婚できる!】と思ったら,実はそうではないのです。
通常の民事訴訟は,相手が期日に欠席し続けるような場合、被告において原告側の主張を自白したものとみなされ(民訴法159条1項),真偽不明のまま欠席裁判が可能となりますが,
離婚訴訟は違います。
離婚訴訟は人事訴訟という類型であり,民事訴訟法159条1項が適用されないとされており(人事訴訟法19条1項),真偽不明のまま欠席判決ができないのです(司法試験の短答式試験でもよく問われる簡単な知識です)。
そのため,立証が必要になってきます。
何を立証するかといえば,離婚訴訟では,民法770条で定められた5つの「法定離婚事由」のいずれかに該当することを立証する必要があります。
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 回復の見込みがない強度の精神病
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な理由
音信不通の場合は長期の別居期間があると思いますので,主に別居期間やそれ以外の事情により婚姻関係が破綻しており,⑤に該当することを主張することになるでしょう。
ここで,当職の経験談を交えて話しますと,調停に続き,相手が訴訟でも欠席したため,訴訟の裁判官から【立証】をするようにとの指示がありました。
基本的にはどう【立証】するかといえば,書証(証拠)を提出して,証拠調べ(原告本人の尋問)となります。
ただ長期の音信不通状態ですと,証拠は証言しかないことが多いです。
そこで,原告本人尋問となりましたが,原告が裁判所に来ることがなかなか難しい事案で,原告の陳述書を提出し,それをもって,【立証】することができました。
そして,後日,勝訴判決を得て,無事判決書が届き,離婚届を出し,離婚成立になりました。
5,離婚の相談
以上経験を踏まえ,音信不通の相手との離婚手続きについてまとめました。
音信不通の離婚手続きについては気軽にご相談くださいませ。
三鷹の弁護士 関真悟
0422-29-6430
メール seki@sekisogo.com
LINE https://page.line.me/566ziisj

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。